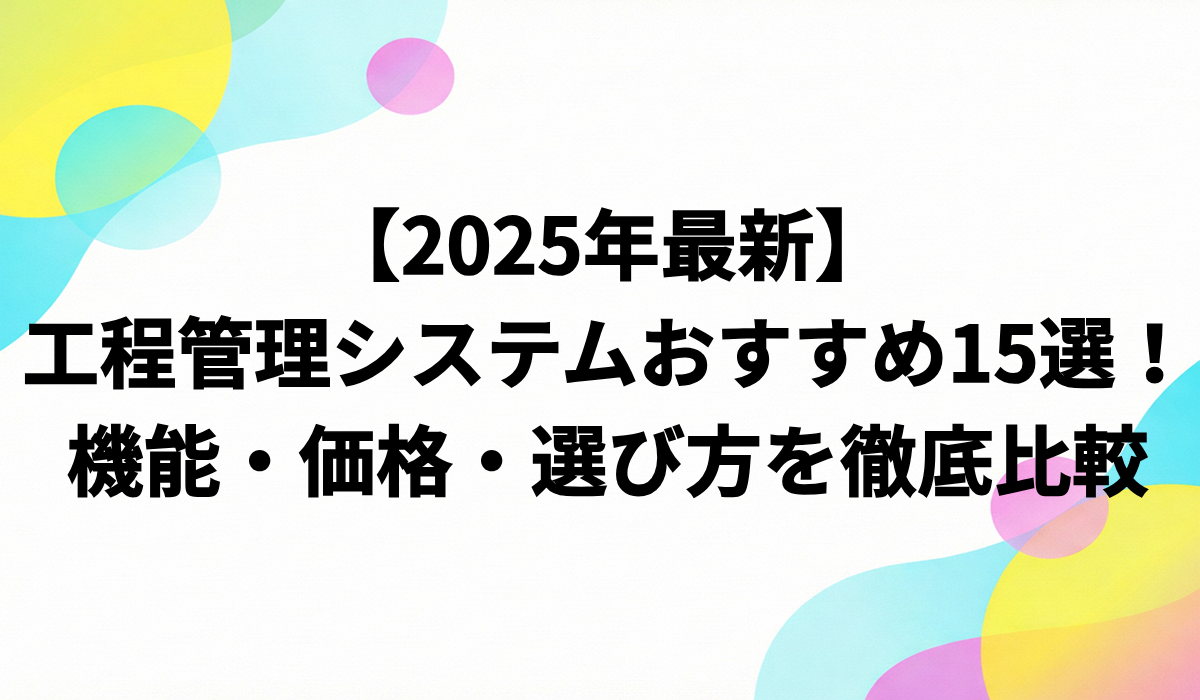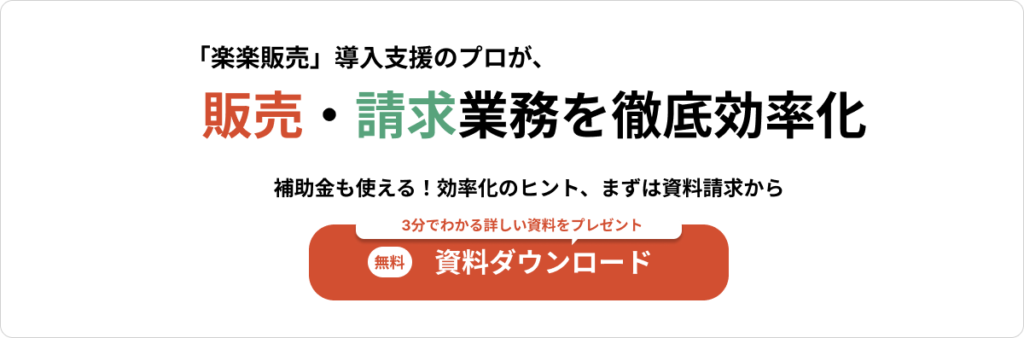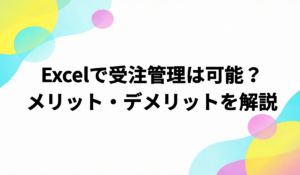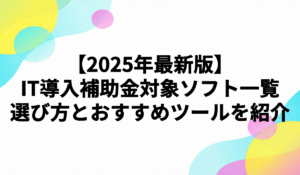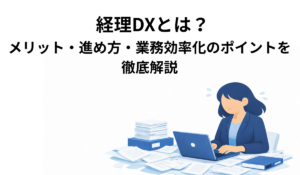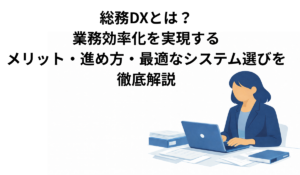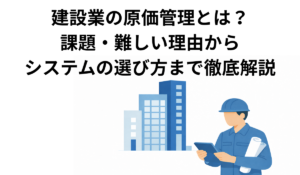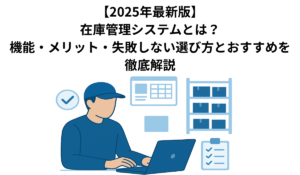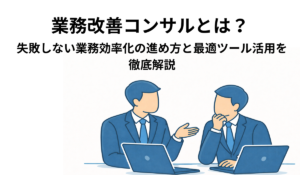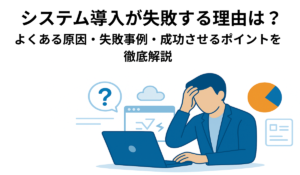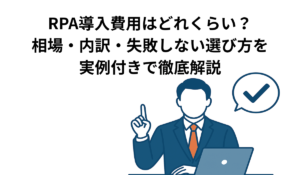「納期が遅れがち」「現場の進捗が見えない」「情報共有がバラバラ」そんな課題を抱えていませんか?
工程管理が属人化したままでは、進捗の遅れや手戻り、認識ズレによるトラブルが頻発し、現場と管理部門の双方に大きな負担がかかります。
こうした課題の解決策として、近年注目されているのが工程管理システムの導入です。
最新の工程管理システムを活用すれば、複雑なプロジェクトや工程もリアルタイムで可視化でき、情報共有の効率化や生産性の向上を実現できます。
本記事では、工程管理システムの基礎知識から、製造業・建設業・IT開発など業種別の選び方、クラウド型とオンプレミス型の違いを解説。
さらに、2025年最新版のおすすめ工程管理システム15選を徹底比較し、導入を成功させるためのポイントまで詳しく紹介します。
工程管理を一元管理できる柔軟な業務設計が可能な「楽楽販売」の資料はこちらから。
工程管理システムとは?基本と導入のメリット

「工程管理システム」は、製造業、建設業、IT開発など、多岐にわたる業種において、プロジェクトや業務の進行を効率的に管理するための重要なツールです。
具体的には、計画の立案から実行、進捗の監視、そして最終的な改善までの一連のプロセスを一元的に管理し、業務の効率化と品質向上を目指します。
このシステムを導入することで、複雑な工程を可視化し、関係者全員がリアルタイムで状況を把握できるようになります。
結果として、納期遅延の防止、コスト削減、生産性向上といった大きなメリットを得られるのです。
工程管理システムが解決する課題
多くの企業が日常的に直面する課題は、工程管理システムの導入によって大きく改善される可能性があります。
手作業や表計算ソフトでの管理では限界があるこれらの課題を、システムがどのように解決するのかを見ていきましょう。
| 具体的な課題 | 工程管理システムによる解決策 |
| 納期遅延の頻発 進捗状況が不透明で、問題発生時の対応が遅れる。 | リアルタイムな進捗可視化 ガントチャートなどで全体の進捗を把握し、遅延を早期に検知して対策を講じる。 |
| 品質のばらつきや低下 作業手順が標準化されておらず、属人化が進む。 | 作業プロセスの標準化 タスク管理機能で手順を明確にし、品質チェック項目を組み込むことで均一な品質を保つ。 |
| コストの増大 手戻りや無駄な残業、過剰な在庫が発生する。 | リソース・予実管理 人員や資材の最適な配分を計画し、実績と予算を比較することで無駄を削減する。 |
| 情報共有の不足 担当者間や部署間の連携がうまくいかず、最新情報が伝わらない。 | 一元的な情報共有基盤 システム上で全ての情報を集約し、関係者全員がいつでも最新の情報にアクセスできるようにする。 |
| 進捗把握の困難さ 手作業でのデータ入力や集計に時間がかかり、リアルタイムな状況把握が難しい。 | 自動的なデータ収集と分析 作業実績を自動で記録し、進捗レポートを生成することで、迅速な状況把握と意思決定を支援する。 |
| リソース配分の非効率性 人員や設備の負荷が偏り、遊休リソースが発生したり、ボトルネックが生じたりする。 | リソース負荷の可視化と最適化 各リソースの稼働状況を把握し、最適な割り当てを計画することで、生産性を最大化する。 |
工程管理システムの主な機能
工程管理システムには、業務を円滑に進めるための様々な機能が搭載されています。
ここでは、特に重要となる代表的な機能をご紹介します。
| 主な機能 | 機能概要 |
| ガントチャート | プロジェクト全体のスケジュールやタスクの期間、依存関係を視覚的に表示し、進捗状況を一目で把握できる機能です。 |
| タスク管理 | 個々の作業(タスク)の担当者、期限、優先順位、ステータス(未着手、進行中、完了など)を詳細に管理します。 |
| 進捗管理 | 計画された進捗と実際の進捗を比較し、遅延や前倒しをリアルタイムで把握できる機能です。 遅延発生時にはアラートを出すことも可能です。 |
| リソース管理 | 人員、設備、資材などのリソースの割り当て状況や負荷状況を管理し、最適な配分を計画・調整する機能です。 |
| 予実管理 | プロジェクトやタスクにかかる予算と実際の費用を比較し、コスト超過のリスクを早期に発見し、管理を最適化します。 |
| 情報共有・コミュニケーション | タスクに対するコメント機能、ファイル添付、通知機能などを通じて、関係者間のスムーズな情報共有と連携を促進します。 |
| レポート・分析 | 蓄積されたデータを基に、進捗状況、コスト、リソース利用率などのレポートを自動生成し、問題点や改善点を分析するための機能です。 |
| アラート・通知 | タスクの期限が迫っている場合や、進捗に遅延が発生した場合など、重要な情報や変更点を関係者に自動で通知します。 |
工程管理システム導入のメリットとデメリット
工程管理システムは多くのメリットをもたらしますが、導入には考慮すべきデメリットも存在します。
これらを理解した上で、自社にとって最適な選択をすることが重要です。
| メリット | デメリット |
| 生産性の向上 無駄な作業の削減、効率的なリソース配分により、全体の生産性が向上します。 | 導入コスト システムの初期費用やライセンス費用、導入コンサルティング費用などが発生します。 |
| 品質の安定・向上 作業プロセスの標準化と可視化により、ミスの削減や品質の均一化が図れます。 | 運用コスト 月額利用料、保守費用、システム管理者の人件費などが継続的に発生します。 |
| コスト削減 手戻りの減少、残業時間の抑制、在庫の最適化などにより、全体的なコストを削減できます。 | 学習コスト 新しいシステムに慣れるための時間や、従業員へのトレーニングが必要になります。 |
| 納期遵守の徹底 進捗状況のリアルタイム把握と問題の早期発見により、納期遅延のリスクを大幅に低減します。 | システム選定の難しさ 多種多様なシステムの中から、自社の業種や規模、要件に合ったものを選ぶのが難しい場合があります。 |
| 情報共有の促進 一元化された情報基盤により、部門間や関係者間のスムーズな連携と意思疎通が可能になります。 | 既存システムとの連携課題 既存の基幹システムや会計システムとの連携がスムーズにいかない場合があります。 |
| 意思決定の迅速化 正確でリアルタイムなデータに基づき、経営層や管理者が迅速かつ的確な意思決定を行えるようになります。 | 定着化の課題 システムを導入しても、従業員が使いこなせず、運用が形骸化してしまうリスクがあります。 |
| 属人化の解消 個人の経験や知識に依存していた業務プロセスがシステム化され、ノウハウが組織全体で共有されます。 |
失敗しない工程管理システムの選び方

適切な工程管理システムを選ぶことは、投資対効果を最大化し、長期的な業務改善を実現するための鍵となります。
しかし工程管理システムには多くの種類があるため、自社に最適なものを選び、導入を成功させるには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、失敗しない工程管理システムの選び方を解説します。
自社の業種・規模に合った工程管理システムを選ぶ
工程管理システムを選ぶ上で最も重要なのは、自社の業種特性と企業規模に合致しているかという点です。
業種によって管理すべき項目や求められる機能が大きく異なるため、汎用的なシステムでは対応しきれない場合があります。
例えば、製造業では生産計画、在庫管理、品質管理、設備稼働状況の可視化などが重視されます。
建設業では、現場の進捗状況、資材管理、協力会社との連携、図面共有機能が求められるでしょう。
IT・ソフトウェア開発では、タスクの進捗トラッキング、バグ管理、バージョン管理、アジャイル開発への対応が不可欠です。
自社の業務フローや課題を明確にし、それに特化したシステムを選ぶことで、導入後のミスマッチを防ぎ、高い効果が期待できます。
また、企業の規模も重要な選定基準です。
中小企業向けには、シンプルで導入しやすい、コストを抑えたクラウド型システムが適していることが多いです。
一方、大企業では、複雑な組織構造や大規模なプロジェクトに対応できる、高度なカスタマイズ性や他システムとの連携機能を備えたシステムが求められます。
将来的な事業拡大を見据え、スケーラビリティ(拡張性)があるかどうかも確認しておくと良いでしょう。
必要な機能と予算を明確にする
工程管理システムに求める機能と、それにかけられる予算を明確にすることは、選定プロセスにおいて非常に重要です。
まずは、自社の現状の課題を洗い出し、その課題を解決するために「どのような機能が絶対に必要か」をリストアップすることから始めましょう。
例えば、以下のような機能が挙げられます。
- ガントチャート作成・進捗管理機能:プロジェクト全体の進捗状況を視覚的に把握し、遅延を早期に発見する。
- タスク管理・担当者割り当て機能:各タスクの責任者を明確にし、作業の漏れを防ぐ。
- リソース管理機能:人員や設備などのリソースの負荷状況を可視化し、最適に配分する。
- 実績入力・予実管理機能:作業実績を記録し、計画との差異を分析する。
- レポート・分析機能:蓄積されたデータを基に、生産性やコストに関する洞察を得る。
- 外部システム連携機能:会計システムやCRMなど、既存のシステムとの連携で業務効率を高める。
多機能なシステムほど魅力的ですが、必要以上の機能はかえって使いこなせず、導入コストや運用コストの増加につながる可能性があります。
本当に必要な機能に絞り込み、優先順位を付けることが肝心です。
予算については、初期費用だけでなく、月額利用料、保守費用、カスタマイズ費用、従業員へのトレーニング費用など、導入から運用までにかかるトータルコストを考慮しましょう。
複数のシステムを比較検討し、費用対効果が最も高いものを選ぶことが重要です。
クラウド型とオンプレミス型の違いと選び方
工程管理システムは、大きく分けて「クラウド型」と「オンプレミス型」の2種類があります。
それぞれの特徴を理解し、自社の運用方針やセキュリティ要件に合わせて選択することが重要です。
| 項目 | クラウド型 | オンプレミス型 |
| 導入費用 | 比較的安価(月額料金制が多い) | 高額 (サーバーやソフトウェアの購入費) |
| 導入期間 | 短期間で利用開始可能 | 長期間 (サーバー構築、設定など) |
| 運用・保守 | ベンダーに一任 | 自社で実施 (専門知識が必要) |
| アクセス | インターネット環境があればどこからでも可能 | 社内ネットワーク内が基本 (VPNなどで外部アクセスも可能) |
| カスタマイズ性 | 限定的、またはオプション費用が必要 | 高い (自社の要件に合わせて柔軟に構築可能) |
| セキュリティ | ベンダーのセキュリティ対策に依存 | 自社で厳格に管理可能 |
| アップデート | 自動で最新機能を利用可能 | 自社で実施 (手間とコストがかかる) |
クラウド型は、初期費用を抑えたい企業や、IT専任者が少ない企業、テレワークなど多様な働き方を推進したい企業に適しています。
手軽に導入でき、運用・保守の手間がかからない点が大きなメリットです。
一方、オンプレミス型は、高度なカスタマイズが必要な企業、既存の基幹システムとの連携を重視する企業、あるいは自社で厳格なセキュリティポリシーを適用したい企業に適しています。
初期費用や運用コストはかかりますが、自社の環境に合わせて柔軟なシステム構築が可能です。
自社の予算、運用体制、セキュリティ要件、そして将来的な拡張性を総合的に判断し、最適な形式を選びましょう。
サポート体制とセキュリティを確認する
システム導入は、購入して終わりではありません。
導入後の運用をスムーズに進め、トラブル発生時に迅速に対応してもらうためには、ベンダーのサポート体制が非常に重要です。
導入前の相談から、初期設定支援、データ移行、操作トレーニング、そして導入後の問い合わせ対応やトラブルシューティングまで、どのようなサポートが提供されるのかを事前に確認しましょう。
特に、システム導入が初めての企業や、社内にITに詳しい人材が少ない場合は、手厚いサポートがあるシステムを選ぶと安心です。
サポートの対応時間、連絡手段(電話、メール、チャット)、日本語対応の有無なども確認しておくと良いでしょう。
また、工程管理システムは、企業の機密情報やプロジェクトの進捗状況など、重要なデータを扱うため、セキュリティ対策も非常に重要です。
データの暗号化、アクセス制限、バックアップ体制、災害対策、そしてSLA(サービス品質保証)の有無などを確認しましょう。
クラウド型の場合は、ベンダーがどのようなセキュリティ認証(例:ISMS認証、プライバシーマーク)を取得しているか、データセンターの所在地やセキュリティ対策はどうかを確認します。
オンプレミス型の場合は、自社のサーバーやネットワーク環境のセキュリティ対策を強化する必要があります。
情報漏洩やシステム停止のリスクを最小限に抑えるためにも、セキュリティ対策は妥協せずに検討すべき項目です。
【2025年最新】工程管理システムおすすめ15選を徹底比較
ここからは、2025年最新の工程管理システムの中から、特におすすめの15製品を業種別に厳選してご紹介します。
各システムの機能、特徴、価格帯、そしてどのような企業に適しているかを詳しく解説します。
自社のニーズに合ったシステムを見つけるための参考にしてください。
【製造業向け】おすすめ工程管理システム
製造業においては、多品種少量生産や短納期化が進む中で、生産計画の最適化、進捗のリアルタイム把握、そして品質維持が極めて重要です。
ここでは、製造現場の特性に合わせた機能を持つ工程管理システムを5つご紹介します。
楽楽販売(株式会社ラクス)

楽楽販売は、株式会社ラクスが提供するクラウド型の販売管理システムですが、販売管理機能と連携して製造工程の進捗管理も可能です。
受注から発注、在庫、売上までの一連の業務を一元管理することで、製造プロセスの見える化を促進し、業務効率化と生産性向上に貢献します。
- 主な機能
受注管理、発注管理、在庫管理、売上管理、工程進捗管理、生産計画、データ連携、各種帳票出力 - 特徴
- ノーコードで柔軟なカスタマイズが可能で、自社の業務フローに合わせたシステム構築が実現します。
- 直感的な操作性で、ITリテラシーが高くない現場担当者でもスムーズに利用できます。
- クラウド型のため、インターネット環境があればどこからでもアクセスでき、情報共有が容易です。
- 価格帯
初期費用と月額費用が発生します。利用ユーザー数や機能によってプランが異なります。
UM SaaS Cloud(シナプスイノベーション)

UM SaaS Cloudは、株式会社シナプスイノベーションが提供する製造業に特化したクラウド型生産管理システムです。
多品種少量生産から量産まで、あらゆる生産形態に対応し、生産計画、工程管理、原価管理、品質管理などを一元的にサポートします。
- 主な機能
生産計画、製造実績収集、工程進捗管理、品質管理、原価管理、在庫管理、購買管理、販売管理 - 特徴
- 製造業の複雑な業務プロセスに対応する高い専門性と柔軟性を持ち合わせています。
- リアルタイムで製造現場の情報を収集・分析し、迅速な意思決定を支援します。
- 他システムとの連携も可能で、既存のシステム資産を活かしながら導入できます。
- 価格帯
初期費用と月額費用が発生します。利用規模や必要なモジュールによって変動します。
ものレボ工程管理(ものレボ株式会社)

ものレボ工程管理は、ものレボ株式会社が提供する、製造現場の工程管理に特化したクラウドシステムです。
現場の進捗状況をリアルタイムで可視化し、ボトルネックを早期に発見・解消することで、生産効率の向上と納期遵守を支援します。
- 主な機能
進捗状況のリアルタイム表示、作業指示、実績入力、負荷状況の可視化、生産計画との連携、タクトタイム管理 - 特徴
- シンプルなインターフェースと直感的な操作性で、現場の作業員でも簡単に実績入力が可能です。
- iPadなどのタブレット端末にも対応しており、現場での情報入力や確認がスムーズに行えます。
- 進捗状況が色分けされて表示されるため、一目で遅延や問題箇所を把握できます。
- 価格帯
初期費用と月額費用が発生します。ライセンス数や利用機能によって異なります。
A-Eyeカメラ(アムニモ株式会社)
A-Eyeカメラは、アムニモ株式会社が提供する、AI画像認識技術を活用した製造現場の稼働監視システムです。
製造ラインの稼働状況や作業員の動作を自動で記録・分析することで、工程管理に必要なデータを非接触で効率的に収集し、生産性改善に貢献します。
- 主な機能
AI画像認識による稼働状況監視、作業時間計測、異常検知、データ分析、稼働率レポート作成 - 特徴
- カメラ映像から自動でデータを収集するため、人手による入力の手間やミスを削減できます。
- リアルタイムで現場の状況を把握し、設備停止や作業遅延などの異常を早期に検知します。
- 収集したデータを基に、ボトルネックの特定や作業改善のヒントを得ることができます。
- 価格帯
初期費用と月額費用が発生します。カメラ台数や利用するAI機能によって変動します。
SmartF(スマートF/株式会社ネクスタ)

SmartFは、株式会社ネクスタが提供する、製造業向けのクラウド型ERPシステムです。
生産管理、販売管理、購買管理、在庫管理、原価管理といった基幹業務を一元化し、工程管理を含む製造プロセスの全体最適化を支援します。
中小企業から中堅企業まで幅広く対応しています。
- 主な機能
生産計画、工程管理、販売管理、購買管理、在庫管理、原価管理、品質管理、予実管理 - 特徴
- 製造業に必要な機能を網羅しており、業務の見える化とデータの一元管理を実現します。
- SaaS型で提供されるため、初期投資を抑えつつ、短期間での導入が可能です。
- 柔軟な設定変更が可能で、企業の成長や業務の変化に合わせてシステムを最適化できます。
- 価格帯
初期費用と月額費用が発生します。利用規模や必要なモジュールによって異なります。
【建設業向け】おすすめ工程管理システム
建設業では、多数の協力会社との連携、資材調達、天候の影響など、多くの不確定要素の中でプロジェクトを進行させる必要があります。
ここでは、建設現場特有の課題を解決し、効率的な工程管理を支援するシステムを5つご紹介します。
現場ナビ工程(構造ソフト株式会社)
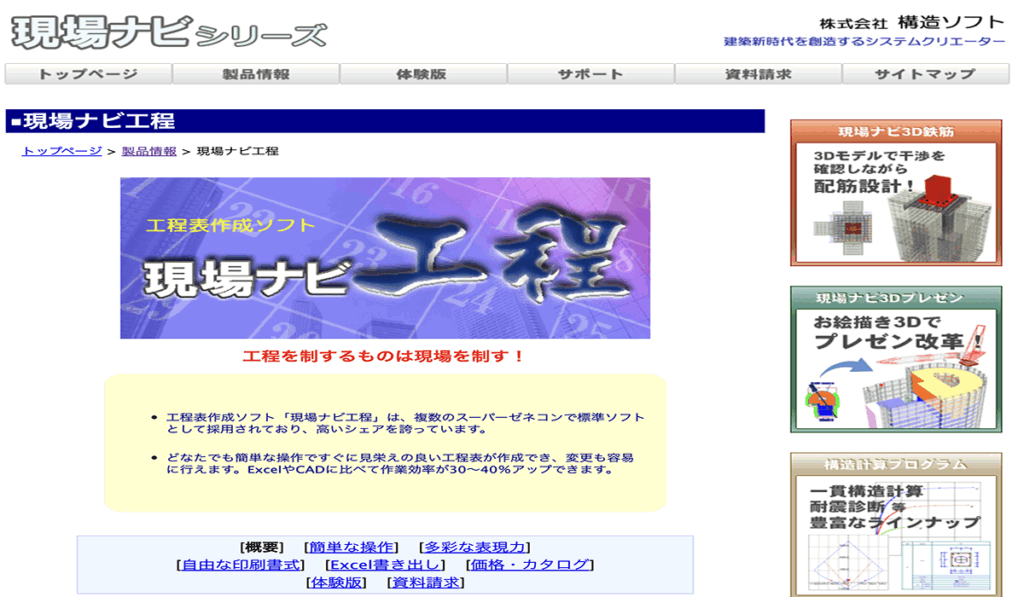
現場ナビ工程は、構造ソフト株式会社が提供する建設業向けの工程管理システムです。
ガントチャート形式で直感的に工程表を作成・管理でき、進捗状況の把握から資源の最適配置までをサポートします。
複数プロジェクトの一元管理にも対応しています。
- 主な機能
工程表作成、進捗入力、資源管理、予算管理、実績管理、帳票出力、複数プロジェクト管理 - 特徴
- 建設業の慣習に合わせた工程表作成機能が充実しており、専門知識がなくても使いこなせます。
- 進捗状況がリアルタイムで反映され、遅延が発生した際には視覚的に把握できます。
- 協力会社との情報共有機能も備わっており、スムーズな連携を促進します。
- 価格帯
ライセンス購入型、または月額費用プランがあります。利用規模によって異なります。
ANDPAD(株式会社アンドパッド)
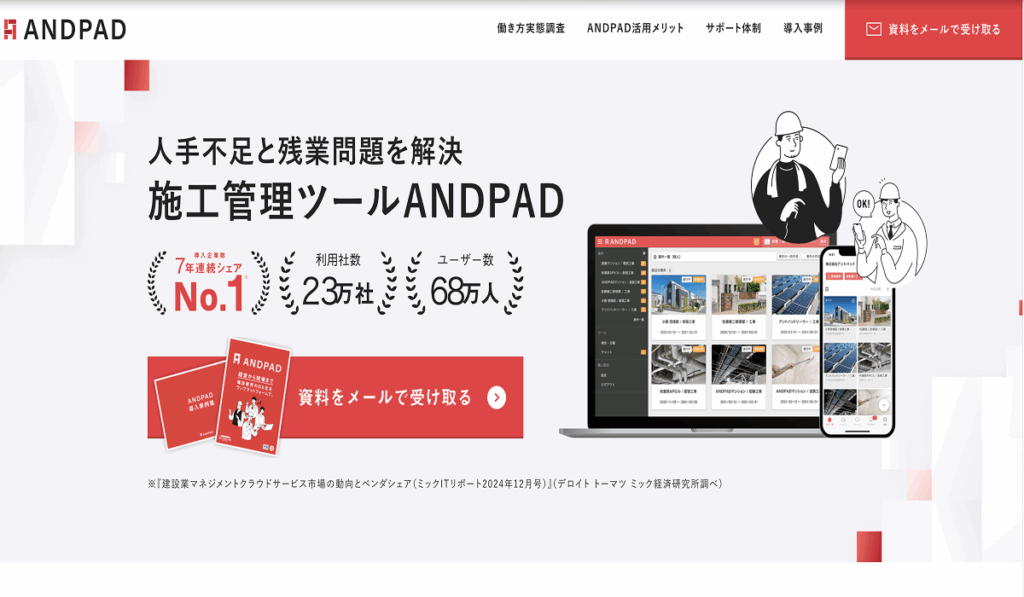
ANDPADは、株式会社アンドパッドが提供する、建設現場の施工管理を総合的に支援するクラウドサービスです。
工程管理だけでなく、写真管理、図面共有、チャット、検査記録など、現場に必要なあらゆる機能を網羅し、情報の一元化と共有を促進します。
- 主な機能
工程表作成・共有、進捗管理、写真・動画管理、図面共有、チャット、日報作成、検査記録、電子黒板 - 特徴
- スマートフォンやタブレットからの利用に特化しており、現場での操作性に優れています。
- 協力会社との情報共有が容易で、コミュニケーションの活性化と業務効率化に貢献します。
- 導入企業数が多く、建設業界での実績が豊富です。
- 価格帯
初期費用と月額費用が発生します。利用ユーザー数や機能によってプランが異なります。
ダンドリワーク(株式会社ダンドリワークス)
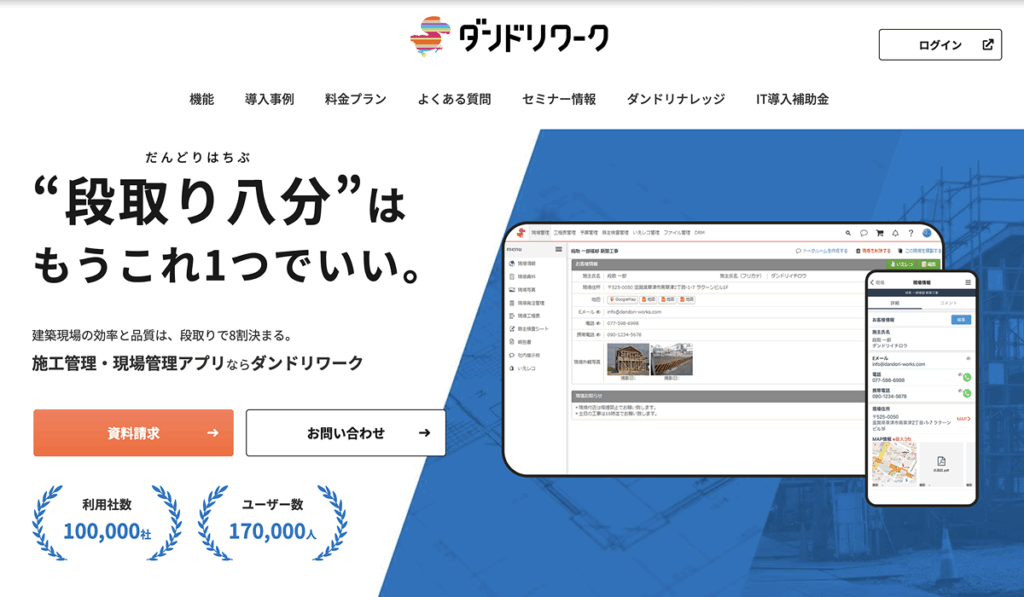
ダンドリワークは、株式会社ダンドリワークスが提供する、建設現場の情報共有と連携を強化するクラウドプラットフォームです。
工程表の共有、進捗報告、図面・資料の共有などを一元化し、現場とオフィス、協力会社間のスムーズな連携を実現します。
- 主な機能
工程表作成・共有、進捗報告、図面・資料共有、連絡掲示板、写真管理、日報、見積もり連携 - 特徴
- 協力会社との連携に強みがあり、情報伝達のミスや遅延を削減します。
- シンプルなインターフェースで、誰でも直感的に操作できるため、導入障壁が低いのが魅力です。
- 現場の進捗状況をリアルタイムで把握し、適切な指示出しや意思決定を支援します。
- 価格帯
初期費用と月額費用が発生します。利用ユーザー数や機能によってプランが異なります。
Photoruction(株式会社フォトラクション)

Photoructionは、株式会社フォトラクションが提供する、建設現場の生産性向上を目的とした施工管理システムです。
写真管理を核としつつ、工程管理、図面管理、検査記録など、施工管理に必要な機能を統合しています。
AIを活用した写真整理機能も特徴です。
- 主な機能
写真管理、工程表作成・共有、進捗管理、図面管理、電子黒板、検査記録、報告書作成 - 特徴
- AIによる写真の自動仕分けやタグ付け機能により、写真整理の負担を大幅に軽減します。
- 高品質な電子黒板機能により、現場写真に正確な情報を効率的に付加できます。
- 工程表と写真・図面が連携しており、進捗状況と紐付けて情報を確認できます。
- 価格帯
初期費用と月額費用が発生します。利用ユーザー数や機能によってプランが異なります。
サクミル(株式会社サクミル)

サクミルは、株式会社サクミルが提供する、建設業向けの工程表作成に特化したクラウドサービスです。
直感的な操作で、見やすく美しい工程表を簡単に作成できることが最大の特徴です。
進捗管理機能も備え、現場の状況をリアルタイムで共有できます。
- 主な機能
工程表作成、ガントチャート表示、進捗管理、PDF出力、共有機能、タスク管理 - 特徴
- ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作で、誰でも簡単にプロフェッショナルな工程表を作成できます。
- 作成した工程表はクラウド上で共有でき、関係者全員が最新情報を確認できます。
- シンプルな機能に絞られているため、導入から運用までのハードルが低いです。
- 価格帯
月額費用が発生します。利用ユーザー数や機能によってプランが異なります。
【IT・ソフトウェア開発向け】おすすめ工程管理システム
IT・ソフトウェア開発の現場では、アジャイル開発やスクラム、カンバンといった開発手法が主流であり、柔軟なタスク管理、迅速な課題解決、チーム間の密な連携が求められます。
ここでは、開発プロセスの特性に合わせた工程管理システムを5つご紹介します。
JIRA(アトラシアン社)
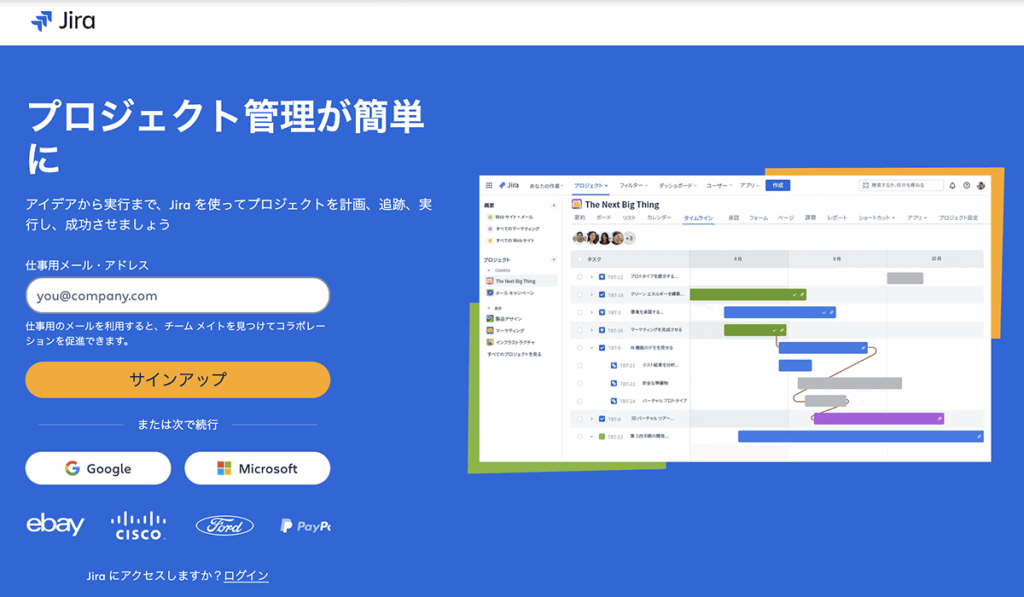
JIRAは、アトラシアン社が提供する、ソフトウェア開発チームに広く利用されるプロジェクト管理・課題追跡ツールです。
アジャイル開発(スクラム、カンバン)に特化しており、タスク管理、バグトラッキング、ロードマップ作成など、開発プロセス全体をサポートします。
- 主な機能
タスク管理、課題追跡、スクラムボード、カンバンボード、ロードマップ、レポート機能、ワークフロー自動化 - 特徴
- 高いカスタマイズ性により、自社の開発プロセスやワークフローに合わせて柔軟に設定できます。
- 豊富な連携機能があり、ConfluenceやBitbucketなど他のアトラシアン製品はもちろん、様々な開発ツールと連携可能です。
- 大規模な開発プロジェクトや複数のチームでの利用にも適しています。
- 価格帯
無料プランあり。有料プランはユーザー数や利用機能によって変動します。
Redmine

Redmineは、オープンソースで提供されているプロジェクト管理ソフトウェアです。
タスク管理、ガントチャート、ロードマップ、Wiki、フォーラムなど、プロジェクト管理に必要な機能を網羅しており、IT開発だけでなく幅広い業種で利用されています。
無償で利用できる点が大きな魅力です。
- 主な機能
タスク管理、課題管理、ガントチャート、ロードマップ、Wiki、ニュース、ファイル管理、時間管理 - 特徴
- オープンソースであるため、無料で利用開始でき、導入コストを抑えられます。
- 豊富なプラグインやカスタマイズオプションがあり、自社のニーズに合わせて機能を拡張できます。
- オンプレミスでの運用も可能で、セキュリティ要件の高い企業でも安心して利用できます。
- 価格帯
無料(導入・運用には技術的な知識が必要、または有償のホスティングサービスやサポートを利用)。
ClickUp
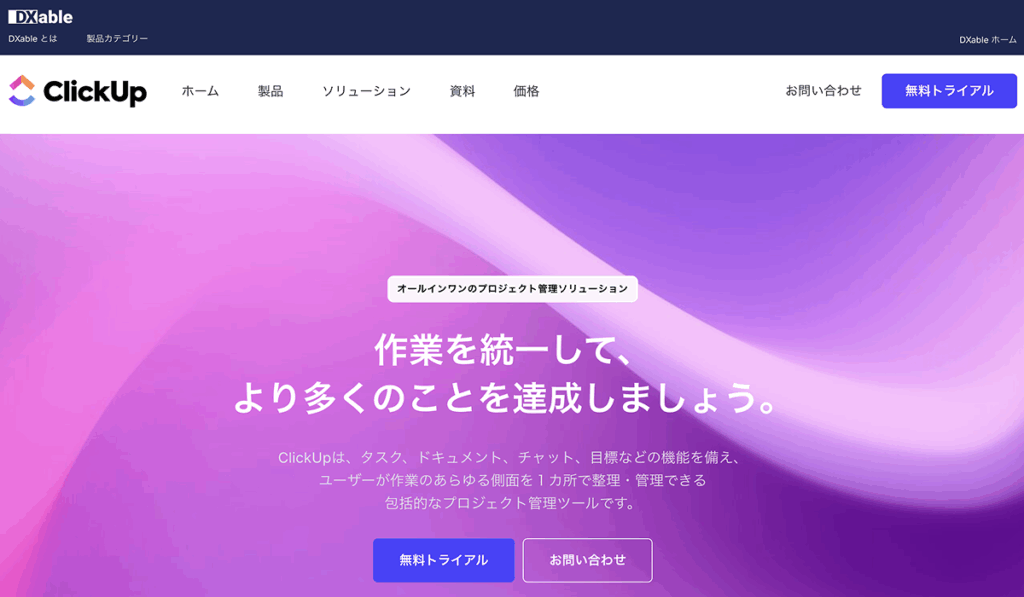
ClickUpは、あらゆる種類のプロジェクトに対応するオールインワンの生産性プラットフォームです。
タスク管理、ドキュメント作成、チャット、目標設定、タイムトラッキングなど、多様な機能を統合しており、IT・ソフトウェア開発チームの生産性向上を強力に支援します。
- 主な機能
タスク管理、プロジェクト管理、ドキュメント作成、チャット、目標設定、タイムトラッキング、ガントチャート、ボードビュー - 特徴
- 高い柔軟性とカスタマイズ性があり、チームの作業スタイルに合わせて様々なビュー(リスト、ボード、カレンダー、ガントチャートなど)を切り替えられます。
- プロジェクト管理に必要な機能がすべて揃っており、複数のツールを使い分ける手間を省けます。
- 無料プランも用意されており、小規模チームや個人でも気軽に試すことができます。
- 価格帯
無料プランあり。有料プランはユーザー数や機能によって変動します。
Asana
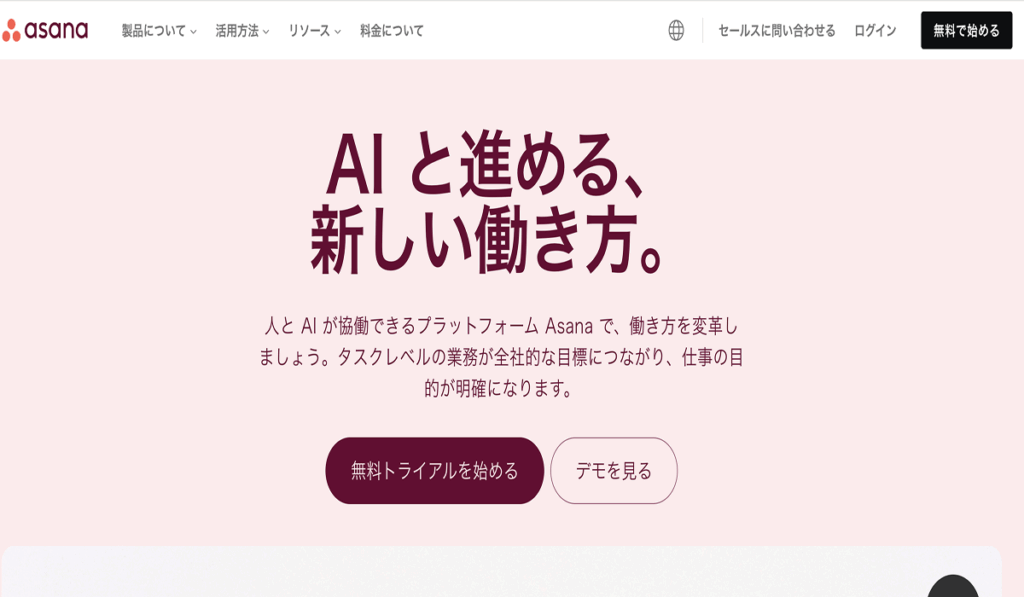
Asanaは、チームのタスクとプロジェクトを整理し、進捗を追跡するためのワークマネジメントツールです。
直感的なインターフェースと豊富な機能で、タスクの割り当て、期日設定、進捗状況の可視化を容易にし、チームのコラボレーションを促進します。
IT開発だけでなく、マーケティングや営業など幅広い部署で活用されています。
- 主な機能
タスク管理、プロジェクト管理、ボードビュー、リストビュー、タイムライン(ガントチャート)、ポートフォリオ、目標設定 - 特徴
- 直感的で使いやすいインターフェースにより、導入障壁が低く、チーム全体での定着がしやすいです。
- タスクの親子関係や依存関係を視覚的に管理でき、プロジェクト全体の流れを把握しやすいです。
- 豊富なテンプレートが用意されており、すぐにプロジェクトを開始できます。
- 価格帯
無料プランあり。有料プランはユーザー数や機能によって変動します。
Trello

Trelloは、アトラシアン社が提供する、カンバン方式を採用した視覚的なプロジェクト管理ツールです。
タスクをカードとしてボード上に配置し、ドラッグ&ドロップで簡単に進捗を管理できます。
シンプルながらも強力な機能で、IT開発におけるタスク管理やアイデア整理に活用されています。
- 主な機能
タスク管理(カード形式)、カンバンボード、チェックリスト、期日設定、ファイル添付、ラベル付け - 特徴
- 非常にシンプルで直感的な操作性により、誰でもすぐに使いこなすことができます。
- 視覚的にタスクの進捗状況を把握できるため、チーム全体の状況が一目で分かります。
- 豊富なパワーアップ(拡張機能)により、カレンダーやタイムライン表示、他のツールとの連携も可能です。
- 価格帯
無料プランあり。有料プランは機能によって変動します。
工程管理システム導入を成功させるためのポイント
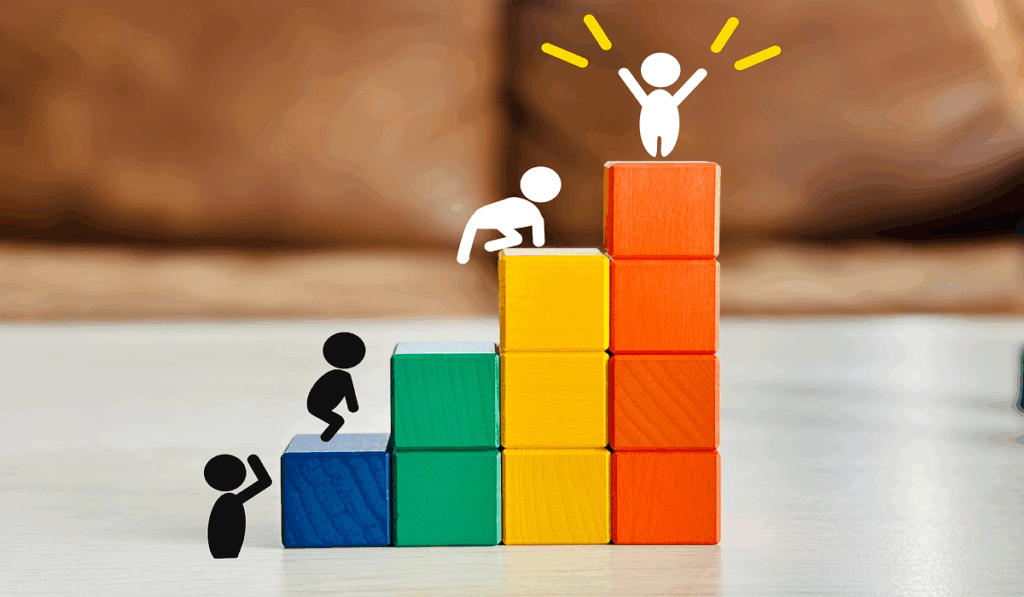
工程管理システムの導入は、単にツールを導入するだけでなく、企業の業務プロセスそのものを最適化し、生産性を向上させるための重要なプロジェクトです。
そのためには、計画的な準備、適切な運用、そして継続的な改善が不可欠となります。
ここでは、システム導入を成功に導くための具体的なポイントを解説します。
導入前の準備と社内体制の構築
システム導入の成否は、事前の準備段階で大きく左右されます。
自社の現状を正確に把握し、明確な目標設定と適切な社内体制を構築することが成功への第一歩です。
1. 現状分析と課題の明確化
まず、現在の工程管理における課題や非効率な点を具体的に洗い出します。
「なぜシステムが必要なのか」「何を解決したいのか」を明確にすることで、導入すべきシステムの要件が見えてきます。
- 現在の工程管理方法(Excel、ホワイトボード、口頭など)の課題
- 納期遅延の原因、手戻りの発生状況
- 情報共有のボトルネック、部門間の連携不足
- 残業時間の多さ、生産性の低い作業
2.目標設定とKPIの策定
システム導入によって達成したい具体的な目標を設定します。
目標は定量的に測定可能なKPI(重要業績評価指標)として定義することが重要です。
| 目標例 | KPI例 |
| 納期遵守率の向上 | 納期遵守率を現状の80%から95%に改善 |
| 生産リードタイムの短縮 | 製造リードタイムを平均20%短縮 |
| 情報共有の効率化 | 工程進捗に関する問い合わせ対応時間を30%削減 |
| コスト削減 | 残業代を年間〇〇円削減 |
3. 要件定義とベンダー選定
現状分析と目標設定に基づき、システムに求める機能や性能を具体的に定義します。
その上で、複数のベンダーから情報収集を行い、自社の要件に最も合致するシステムを選定します。
- 必要な機能リスト(ガントチャート、進捗管理、リソース管理、原価管理など)
- 既存システムとの連携要件
- カスタマイズの必要性
- ベンダーのサポート体制、実績
4.社内体制の構築と関係者への説明
システム導入プロジェクトを推進するための専任チームを結成し、各部門からの代表者を含めることで、全社的な視点での導入を進めます。
また、導入の目的やメリットを関係者全員に丁寧に説明し、理解と協力を得ることで、導入後のスムーズな移行を促します。
- プロジェクトリーダーの任命
- 各部門からのキーパーソンの選出
- 定期的な情報共有会の実施
運用定着のためのステップ
システムを導入しただけでは、その効果は最大化されません。
従業員がシステムを日常的に活用し、業務に定着させることが成功の鍵となります。
1. 導入計画の策定とデータ移行
詳細な導入スケジュールを作成し、各工程の担当者と役割を明確にします。
特に、既存の工程データや顧客データなどの移行は慎重に行う必要があります。
データの整合性を保ちつつ、スムーズな移行計画を立てましょう。
- データ移行の範囲と方法の決定
- 移行期間中の業務への影響を最小限に抑える計画
- 移行後のデータ検証
2. 従業員への研修とマニュアル作成
システムを実際に利用する従業員への研修は、最も重要なステップの一つです。
システムの操作方法だけでなく、新しい業務フローやシステムの活用によって得られるメリットを具体的に伝えることで、利用意欲を高めます。
| 研修のポイント | マニュアル作成のポイント |
| 対象者に応じた研修内容(管理者向け、一般ユーザー向け) | 画面キャプチャを多用した視覚的に分かりやすい内容 |
| 実践的な演習を取り入れる | よくある質問(FAQ)やトラブルシューティングを盛り込む |
| 疑問点をすぐに解決できるサポート体制の構築 | 定期的な更新とバージョン管理 |
3. テスト運用とフィードバックの収集
本格運用前に、一部の部署やプロジェクトでシステムをテスト運用し、実際の業務で発生する問題点や改善点を洗い出します。
現場からのフィードバックを積極的に収集し、システム設定や業務フローに反映させることで、より実用的なシステムへと磨き上げます。
- テスト期間と対象範囲の明確化
- フィードバック収集の仕組み(アンケート、ヒアリング)
- 問題点の優先順位付けと改善策の検討
4. 段階的な導入と運用ルールの徹底
可能であれば、全社一斉導入ではなく、部門ごとやプロジェクトごとに段階的に導入を進めることで、リスクを分散し、問題発生時の影響を最小限に抑えることができます。
また、システム利用に関する明確な運用ルールを定め、全従業員に徹底させることが、データの一貫性と正確性を保つ上で不可欠です。
- データ入力の基準、更新頻度
- 権限管理、アクセスルールの明確化
- システム活用におけるベストプラクティスの共有
導入後の効果測定と改善
システム導入は一度きりのイベントではなく、継続的な改善を通じてその価値を最大化するプロセスです。
導入後の効果を定期的に測定し、PDCAサイクルを回すことで、常に最適な状態を維持します。
1.定期的な効果測定とKPIの確認
導入前に設定したKPIに基づき、システムの運用状況と効果を定期的に測定します。
数値データを客観的に分析することで、システムが目標達成に貢献しているか、あるいは新たな課題が発生していないかを確認します。
- 週次、月次、四半期ごとのレポート作成
- KPIの達成状況と目標値との比較
- 現場の作業効率、残業時間の変化
2. 課題の特定と改善策の実施
効果測定の結果、目標達成に至っていない点や、運用上で発生している問題点を特定します。
例えば、「特定の機能が使われていない」「入力の手間がかかりすぎている」などの課題に対し、具体的な改善策を検討し、実行に移します。
| 課題例 | 改善策例 |
| 特定の機能が活用されていない | 再研修の実施、利用促進キャンペーン、マニュアルの改善 |
| データ入力に時間がかかり、負担になっている | 入力フォームの簡素化、自動入力機能の活用、既存システムとの連携強化 |
| 進捗状況がリアルタイムに反映されない | 入力ルールの再徹底、システム設定の見直し、モバイルアプリの活用 |
3. ユーザーフィードバックの継続的な収集
システムを使う現場の声は、改善に直結する貴重なヒントです。
定期的なアンケートやヒアリング、ユーザー会などを通じてフィードバックを継続的に収集し、システムの改善や機能追加の参考にします。
ユーザーの意見を積極的に取り入れる姿勢が、システムの定着と満足度向上につながります。
- 定期的なユーザーアンケートの実施
- 部門責任者からのヒアリング
- 改善提案制度の導入
4. システムの最適化とアップデート
業務環境の変化や技術の進歩に合わせて、システムを常に最適な状態に保つことが重要です。
ベンダーからのアップデート情報に注意を払い、必要に応じてシステム設定の見直しや機能追加を検討します。
これにより、長期的な視点で工程管理システムの価値を最大化できます。
- ベンダーからの新機能やアップデート情報の確認
- システムの利用状況に応じた設定変更
- 新たな業務要件に対応するための機能拡張
まとめ
本記事では、2025年最新の工程管理システムおすすめ15選を、機能・価格・選び方とともに徹底解説しました。
工程管理システムは、業務の可視化、効率化、生産性向上に不可欠であり、現代のビジネスにおいて競争力を高める上で重要なツールです。
自社の業種や規模、必要な機能を明確にし、サポート体制やセキュリティ面も考慮して選ぶことが成功の鍵となります。
導入前の準備から運用定着、効果測定まで計画的に進めることで、最大限の効果を引き出し、企業の成長に繋げましょう。